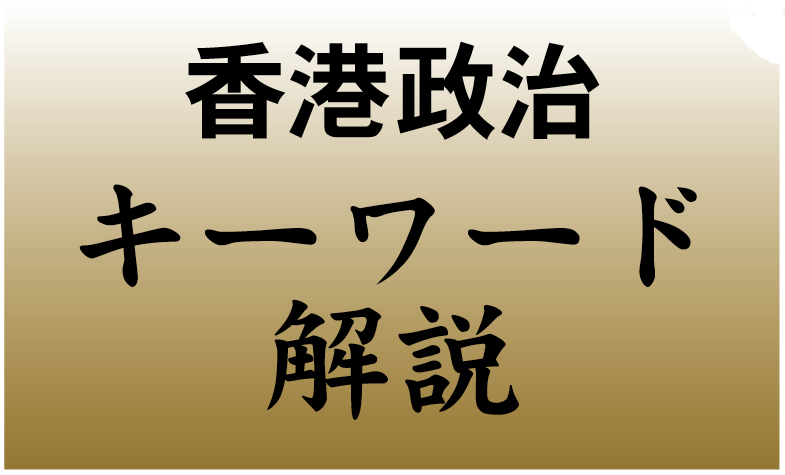
《128回》
融入
(とけ込む)
香港メディアの香港政治関連の報道では、香港ならではの専門用語や、広東語を使った言い回し、社会現象を反映した流行語など、さまざまなキーワードが登場します。この連載では、毎回一つのキーワードを採り上げ、これを手掛かりに、香港政治の今を読み解きます。(立教大学法学部政治学科教授 倉田徹)
香港と本土の経済協力
「中港融合」から新段階へ

主導権はますます中央政府に
「融合」の新たなステージ
今回のキーワードは「融入」、「とけ込む」という意味の中国語です。香港と中国本土の関係を論じる際に、かつては経済「融合」という言葉が主流でしたが、昨年以降新たに「融入」が登場しました。例えば、昨年3月の北京での全国人民代表会議(全人代)の際、全人代委員長の張徳江氏は香港の代表団に対し、香港が「中国の夢に『融入』し、香港の夢を実現する」ことを願うと発言しています。昨年7月1日の、返還20周年式典の講話では、習近平・国家主席が「祖国の胸に戻った香港は、すでに中華民族の偉大な復興の壮大な遠征の道のりに『融入』した」と述べました。
二つのものが対等に合わさってゆく「融合」と比較して、「融入」という言葉には、一方が他方にとけ込み、混ざり込んでゆくというニュアンスがあります。尖沙咀のフェリーターミナルの「中港城」という名前が示すように、香港では当たり前のように使われてきた「中港」という言葉も、近年特に本土では中国と香港を対等の立場のように描写するものとして忌避されます。代わって登場したのが、香港が本土に「融入」するという形容です。
実態として、中国経済の成長により、規模の面では到底並列には論じられない香港と中国本土の経済協力は、「融入」の性質を強く帯びるようになっています。広州—香港間の高速鉄道の開通も、そういう事例のように思えます。中国はすでに世界一の路線延長を誇る高速鉄道網を持っています。ここに広州から香港の支線が接続されることは、まさしく香港が中国の鉄道網に「融入」する現象ということができるでしょう。
「融合」から「融入」へ:経済関係の展開
戦後の本土と香港の経済関係は、その時々で様々な形に変貌してきました。冷戦期は両地の分断の下で、香港が突出した経済成長を見せました。両地の経済の分断状況が変化したのは、中国の改革・開放政策が始まり、深&`経済特区が設置された1980年代のことです。香港の製造業は、安価な土地と労働力を求めて工場の大部分を本土に移しました。香港には管理部門や製造業に関連するサービスだけが残りましたが、両地は互いに優位性を補う形でウィン・ウィンの関係を築きました。これは「前」の香港に「店」すなわちオフィスが、「後」背地の本土に「廠」すなわち工場があるという、「前店後廠」方式と称されました。このころの両地の関係は、結びつきは強化されたものの、融合というよりも分業体制でした。
しかし、返還後になると、軽工業を中心とする本土での香港資本の製造業が競争力を失っていく一方、中国経済は順調に成長を続けました。返還直後のアジア通貨危機の発生や、2003年のSARSの流行で香港経済が危機的状況に陥ると、中央政府は香港特区政府からの要請を受けて「自由貿易区」構想を検討し、「経済貿易関係緊密化協議(CEPA)」の締結に到りました。香港の金融機関での人民元業務の実施や、本土からの個人観光客の大量流入などが始まり、「中港融合」が本格的に論じられるようになりました。この頃の「中港融合」は、香港経済の支援策という色彩が強く、香港とライバル関係にある広東省の都市は香港への譲歩を迫られました。香港・珠海・マカオを結ぶ港珠澳大橋に接続を求めた深&`が、香港の反対でこれを断念させられたのが典型例です。
最近中国の「国策」に位置づけられる「粤港澳大湾区」は、珠江デルタと香港・マカオの一体化を進めるもので、一見すると「中港融合」の延長線上にあるように見えます。しかし、今回は本土の国家計画の用語の「錯位発展」という言葉が使われていることが一つの特徴でしょう。ここでの「錯」は、「ずれる」あるいは「避ける」という意味で、域内の各都市がそれぞれ優位性を発揮する一方で、他者の邪魔にならないように、譲るべき分野では譲るという意味です。香港の場合、「大湾区」の経済の牽引役として、国際金融センターとしての役割を発揮することが求められますが、競争で後れをとりつつあるコンテナ埠頭などは、むしろ深&`に譲ることとなります、香港のための「融合」ではなく、中国経済全体の利益を中央政府が判断して、そこに香港が組み込まれるという、まさに「融入」の計画なのです。
「融入」は本当に可能か
しかし、これまでの「中港融合」がその後たどった道を考えると、北京の計算通りに香港を中国経済に「融入」させられるのか、疑わしいと言わざるを得ません。
「粤港澳大湾区」は、香港人が本土に住み、働くことを奨励することも構想しています。しかし、本土で働く香港人は2004年をピークに減少しています。かつて本土では、工場での熟練工や管理職などの形で香港の人材を必要としていましたが、これは今や本土の人材で補えます。一方、中国経済には新たな起業などのチャンスが多数あるかもしれませんが、普通話を流暢に話し、中国の特殊な国情をよく理解する本土住民と比べて、香港人に優位性はありません。本土に「北上」して夢を追うことは、多くの香港の若者にとってあまり現実的な選択肢ではありません。
他方、香港の医療や福祉などの高度で質の高いサービスには、本土にも大いに需要がありますが、これらを求める人々は自ら個人旅行を利用して本土から香港に南下してくるようになっているため、香港人が制度の壁を乗り越えて苦労して本土で開業する必要性が薄く、むしろ香港にいるほうがブランド力を発揮しやすいのです。北京の政策も、一方では香港人が本土で働く際の「就業証」取得義務の廃止という利便化を図りながら、他方では年間183日以上本土に住んだ香港人に本土での納税を求める新措置の導入を進めるなど、ちぐはぐな感がぬぐえません。
そして勿論忘れてはならないのは、急速な「中港融合」が、かつて香港市民の生活に悪影響を与え、政治問題化したという教訓です。新段階の「融入」の成否においては、ますます主導権をとるようになった中央政府の知恵が試されていると言えるでしょう。
(このシリーズは月1回掲載します)
筆者・倉田徹
立教大学法学部政治学科教授(PhD)。東京大学大学院で博士号取得、03年5月~06年3月に外務省専門調査員として香港勤務。著書『中国返還後の香港「小さな冷戦」と一国二制度の展開』(名古屋大学出版会)が第32回サントリー学芸賞を受賞
