|
あなたが四川省へ行くべき36の理由
第8回 険しい地形に育まれた歴史と食文化 四川省は中国の内陸部にあり、山に囲まれた豊かな自然の中で、独自の文化を育んできた古い歴史を持つ地域です。近年、四川省は経済発展に伴い交通網が整備され、改めて「観光地」として注目を集めています。変貌する「蜀の国」を旅しながら、中国の今を探ってみました。(編集部)
山に囲まれた四川盆地にあって、成都から北へ向かい、徳陽を過ぎ、綿陽を離れると、途端に空気が澄んでくる。山々が目の前に迫ってくる。更に北へ進めば四川盆地が終わる。いつ雨が降り出すかわからない曇り空を眺めながら、深緑の木々に囲まれた山道を車で走っていると、世界の果てに向かっているような気分になってくる。
四川盆地の西側にはチベット高原が広がり、北側には甘粛省や寧夏回族自治区がある…つまりイスラム教の世界だ。四川盆地の北端は、漢民族世界の「端っこ」とも言えるだろうか。これから向かう梓潼県(しとうけん)の七曲山大廟は「別世界」に接する一歩手前にある。なぜこんなところに「観光名所」があるのだろうか。 《24》七曲山大廟 山道の途中に突如、真っ赤に塗られた、大きく立派な建物が現れた=①。 七曲山大廟は道教の施設で、学問の神である「文昌帝君」を祀っている。かつては科挙の受験生やその親から信仰を集め、今も多くの受験生やその親が合格祈願のために訪れる。入り口に「帝郷」と書かれた扁額が掲げられているが、これは「文昌帝君」信仰の発祥地を意味しているそうだ。 七曲山大廟の歴史を紐解くと、五胡十六国の時代にさかのぼる。西暦373年に前秦が益州(四川盆地と漢中盆地一帯)を占領した。その翌年に「蜀王」を自称し反乱を起こして戦死した「張育」という人物がおり、彼が挙兵したのがこの地であった。その張育を祭ったのが七曲山大廟の始まりで、その後に土地神の梓潼神と星神の文昌星を習合し、「文昌帝君」になったという。 四川省を旅するうちに気付いてきたのは、この土地独特のアイデンティティーである。「島国根性」という言葉があるように、「盆地根性」もあるのだろう。四川省は中国の一部ではあるものの、他の中国の地域よりも強固に、「蜀は蜀である」という意識が発達しているような気がする。そうした意識が三国志の蜀漢に投影されたり、この七曲山大廟に祭られている文昌帝君に結晶しているのではないか。 要するに、ここは本来、志半ばに斃れた「蜀王」の廟である。張育は侵略者に抵抗した郷土の英雄なのだ。ただ、これらの「事情」を率直に出してしまうと、時の中央政権から見れば好ましくない。張育は外部の権力に抵抗する「蜀人治蜀」のシンボルなのだから。 そのため、後世に土地神や星神を習合させ、時代に合わせてその役割を変化させたのではないか…そう考えると、扁額の「帝郷」も、別の意味に思えてくるのだ。
七曲山大廟の中に入ると、立派な階段があり、その上に文昌正宮殿がある=②。階段の真ん中に龍が彫られているのは、「御道」と言って皇帝の通り道である。北京の故宮にも同様のものが見られる。つまり、ここは蜀王の「皇宮」なのだろう。 七曲山大廟の歴史を改めて読むと、ここで文昌帝君の祭祀が始まったのは、宋元の時代という。つまり蒙古の南宋侵攻が始まったころだ。蒙古の脅威が近づく中、蜀人の心の拠り所として郷土の英雄・張育を讃え始め、文昌祭祀に発展したのかも知れない。 そして、七曲山大廟が現在の形になったのは明の時代以後…つまり漢民族が蒙古から統治を取り戻した後である。文昌正宮殿は明代に建てられたが、清代に一度焼失し、再建された。 現在の七曲山大廟は、主に合格祈願や学問成就を願うもので、日本の太宰府天満宮のような場所であるが、歴史をひも解いて考えると、蜀人のための国家鎮護、もしくは蜀の「楠木正成」を祭った場所…みたいに思えてくる。 ただし、ここは文化大革命の時に大規模な破壊を受けたらしく、どこまでが明清の時代のままなのか、どこからが文革後に修復されたものなのか、よくわからない。祭られている文昌帝君の像は金箔を張られて全身金ピカで、正確にはいつの時代のものかは不明である。そこで、清代に焼失した正殿から離れたら、明代のままの、文革時に破壊されなかった文物があるのでは…と考え、正殿を出た。
すると、屋外の欄干の上に古い彫像があるのをみつけた。最初に見つけたのはブタのような…いや、よく見ると頭の上に耳のようなものが見えるし、鼻の横には長いヒゲが描かれている…これはウサギであろう。もしかしたらこれは、明の時代か、清の時代に作られたものではないのか? 写実的ではないが、ユーモラスながら古風なたたずまいである=③。 次に、同じく欄干の上でよくわからない形の動物を見つけた…これは…たぶんカエルではないか?=写真④ 背中の文様といい、きっとそうに違いない。当時は石材加工の技術も限界があって、こうしたデフォルメした形状になるのだろうけど、明か清の時代の中国人の職人がカエルを作ると、現代のわれわれから見ても、なんとも言えずカワイイものになるのは面白い。 次に見つけたのは…これはゾウだろう=⑤。さっきのウサギやカエルに比べると、結構リアルな形をしている。明や清の、まだ写真やテレビやネットも無い時代の中国人が、どのようにしてゾウの形を知ったのか。 ちょっと調べてみると、長江以南の地域には古くからアジアゾウが生息しており、四川省にもアジアゾウがいたらしい。明の時代まで生息していたかは不明だけれど、仏教の関連で、ゾウの石像を作ることはあっただろうし、中国に仏教が伝来したころには、アジアゾウは普通に生息していたようだから、過去に作られたゾウの石像を複製したのかもしれない。 その次に見つけたのは…顔が一部削られているけれど、耳の形や腕や背中の模様から考えてこれはトラだろう=⑥。ほかにも小さな人物像の首が切断されているものもあり、これらは文革の時に破壊されたものと思われる。 それにしても、なぜウサギとカエルとゾウは破壊されず、トラは破壊されたのか。トラは強そうなので、権威や権力の象徴として「破四旧」(文革時の旧思想、旧文化、旧風俗、旧習慣を破壊する運動)の対象になったのか。もしくは紅衛兵も、ここのウサギやカエルやゾウの形にはかわいらしさを覚えて壊すのをためらったのか…。 その正しい答えはわからないものの、七曲山大廟は、「蜀」を歴史的にみつめる上で、非常に興味深い場所なのであった。
《25》翠雲廊景区と漢徳駅 七曲山大廟を出て、剣閣県に向け車を走らせる。車窓からの光景には、深緑の木々が延々と続いている。この一帯は「翠雲廊」と呼ばれる柏の群生する広大な森林地帯で、その北端は本連載第6回で紹介した昭化にあり、西端が先ほどの七曲山大廟、その中心部がこれから向かう剣閣県になる。 「全景図」のイラストを見ればわかるように、このような険しい地形から「剣閣県」という名前になったそうだ=⑦。
「全景図」の右端に赤い●が見える。翠雲廊景区である。ここは翠雲廊の中でも多くの古い巨木がある場所として国の重点風景名勝区に指定され、国家森林公園にもなっている。翠雲廊全体では柏の木が10万本あるともいわれている。一説によれば、秦の始皇帝が植樹を命令したのに始まるというから、2200年ぐらいの歴史があることになる。 翠雲廊景区の中はとても広く、どこまでも大きな柏の木が続いている=⑧。説明書きを読むと、樹齢千年、二千年のものらしい。木が好きな人にとって翠雲廊は、興味深い場所だろう。木に興味がない人でも、樹齢何百年以上の木が立ち並ぶ景観には、圧倒されること間違いなしである。ただし、ここにはもう一つの特筆すべき「見どころ」がある。 翠雲廊景区の中には「漢徳駅」という建物がある=⑨。これは鉄道駅ではない。昔の中国や日本には「駅制」というのがあり、通信網の一種であった。 昔の電信も電話もネットもない時代は、政府の文書や軍事情報を人や馬で走って伝えていた。一定区間ごとに「駅」が置かれて、官吏や使者が休憩したり、替わりの馬が待機している。
中国では3千年~4千年ぐらい前から駅制が始まり、始皇帝のころに十里(約4000メートル)ごとに「一亭」設ける取り決めとなった。この時の移動手段は人が歩くので「亭」なのだろう。前漢の時代から馬が使われるようになり、三十里(約12キロ)ごとに「一駅」設けるようになり、その後、全国に駅が設けられたが、現在はほとんど残っていない。 西暦217年に劉備はこの地に漢徳県を置き、それから漢徳駅を設置した。 建物は復元されたものだが、駅道は昔のものらしい=⑩。今まで小説や文献で駅制について読むことは何度もあったが、本物の駅道を見るのは初めてだ。意外に小さい。早馬を飛ばして文書を運んだり伝令が走るだけの道なので、一頭の馬が走れる程度の幅しかないし、舗装はされていない。劉備は北からの魏の侵攻に備えてこの漢徳駅を整備したらしい。かつて蜀漢の兵の早馬が、ここを走った。私は今、その道の上にいるのだ…と思うと、感無量であった。
《26》剣門関と豆腐 剣閣県は「剣閣」よりも「剣門」という地名でよく知られている。それは「剣門関」という関門が有名だからだ。古くから、「剣門関を得れば四川を得る」と言われ、蜀北部の防衛の要衝とされてきた天険の要害である。この剣門関の険しい地形を見ていると、この地の歴史と人々の生活が見えてくるようだ。 剣門関は写真で見ると、断崖絶壁に挟まれた間に小さな城閣…門が1つあるだけだ=⑪。写真でこの関門の外見を見ただけでは、何がスゴいのかはよくわからないだろう。
剣門関の楼閣に登って見下ろすと一目瞭然である=⑫。細く急な坂道を見下ろすようになっており、この道の周囲には巨木もない。関門の上から矢を射掛けられたら身をかわす場所もない。李白の詩に「一夫当関、万夫莫開」(一夫関に当たるや万夫も開くなし)と詠まれた剣門関だが、確かにそれは誇張ではない。実際に、剣門関では近代兵器が出現する以前、百回以上の攻防が繰り広げられたが、正面からの攻撃では1度も陥ちたことがないのだ。
ネットで「剣門関」で地図を確認すればすぐにわかることだが、山に囲まれた四川に北部から侵入しても、剣門関を通らなければ、成都に抜ける最短コースを大きく迂回することになる。剣門関は有史以来、蜀の安全保障の最前線として、地政学的な「宿命」を背負い続けてきた場所なのだ。そう考えると、ここに諸葛孔明が関門を建設したのも、付近に劉備が漢徳駅を設置したのも当然であるし、その150年後、蜀王・張育が、前秦の侵略に抵抗し、剣門関の南西にある梓潼県で挙兵したのも「宿命」のためなのであろう。
剣門関の付近では、どこに行っても石臼が見られる=⑬。剣門関古鎮の入り口にも、レストランにも石臼が飾られている。険しい地理的環境にある剣門関では、昔から豆や芋、トウモロコシ、雑穀などがよく作られた=⑭。それらを粉にして食べるために石臼が使われていたのだ。そのためか、石臼は剣門関の象徴となっている。 加えて、剣門関では湧水に恵まれたので、昔から豆腐作りが盛んである=⑮。剣門関で豆腐が作られたのは三国時代にさかのぼり、三国志にちなむ伝説もある。 蜀の将軍であった姜維が北伐に出たところ、漢中で魏軍に撃退され、剣門関まで退却してきた。その時ここの地方官が、兵馬を休めることを進言し、この地の住民たちに豆乳を作るように命じた。兵は豆腐を食べ、馬はオカラを食べて迅速に体力を取り戻し、三日後に姜維は再び兵を率いて魏軍を破った…という。 つまり、石臼も豆腐も、剣門関では蜀の安全保障と深いかかわりがあるのだ。 ただ、現代の日本人であるわれわれが、「豆腐を食べて兵が体力を取り戻した」と聞いても、あまり実感がない。そこで、剣門関の市場で豆腐を確かめて見たところ、この地で作られている豆腐は、かなり重量感があるのがわかった。豆を大量に使って作られているようで、全く水っぽさが見られない、ズッシリと重い豆腐である。日本でも昔はこういうしっかりした豆腐が売られていたが、今はあまり見かけなくなった。確かにこれだけしっかりした豆腐なら栄養満点だ。疲れた兵士も元気を取り戻すだろうし、おからは充分に馬の餌となったであろう。
しかし…剣門関古鎮の建物が、やけに「雰囲気」がありすぎるのが気になった。正直に言うと、まるで映画のセットかテーマパークの中にいるような感じだ=⑯。中国では、この十数年来「古鎮」ブームというのがあり、古い郷村が観光地として人気を呼んだが、そのブームを当て込んで、新たに作られた「古鎮」もある。 剣門関古鎮の建物は、昔ながらの古い作りだが、どう見ても真新しいものにしか見えない。歴史のある古い土地なのは確かだが、何百年も前の建物がずっと残っているのではないのだろう…と思いつつ古鎮を歩いた。すると、奇妙な龍の像があるのに気がついた。近づいてみると、台座に碑文をみつけた=⑰。
2008年5月12日に発生した四川大地震の際、この地は甚大な被害を受け、中国共産党中央と国務院は黒竜江省に剣閣県の救援と再建を命じた。黒竜江省は復興のために15億元を投資し、その内1.5億元が観光資源の復興にあてられ、剣門関古鎮の改造はその1つ…座龍の像はその記念碑だったのだ。 碑文を読み終えてから、もう一度周囲を見渡し、剣門関古鎮をじっくりと眺めた。私が「真新しい」と思っていたこれらの建物は、地震の後に作られたものなのか…。 剣門関古鎮はかなり大きく、真新しく見える建物も少なくないのだ。元々そこにあった建物は全て損壊したのか…それを想像すると、地震の巨大な破壊力を目の当たりにするようで、総身寒気立って戦慄した。それと同時に、たった6年で険しい山奥の村を、ここまで復興させた中国人の努力に、深く尊敬の念を抱かざるを得なかったのである。(つづく) |
|
|
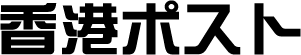

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)